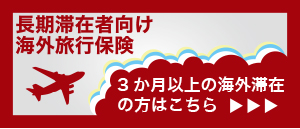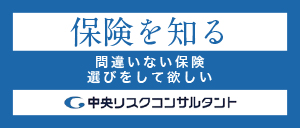高村光太郎、明治に生きたフェミニスト
2012年07月30日 category:ゴルフモード・カルチャー「銅とスズとの合金が立ってゐる。どんな造型が行はれようと無機質の図形にはちがひない。(中略)いさぎよい非情の金属が青くさびて地上に割れてくづれるまでこの原始林の圧力に堪えて立つなら幾千年でも黙って立ってろ」
十和田湖を最も美しく見ることができるとされる休屋。ここから湖畔を見つめる一対の裸婦のブロンズ像。詩人として、彫刻家として名を馳せた高村光太郎の遺作となった『乙女の像』がこの地に立って60数年になる。昭和28年秋に完成し、高村光太郎は翌29年、雑誌『婦人公論』に冒頭の詩「十和田湖畔の裸像に与う」を寄稿した。
生死を繰り返し、永遠の再生を繰り返す雄大な十和田の大自然。その傍に立つ、人工的な自らの像。高村光太郎自身も、物質である乙女の像も「限りのある、一度きりの命」。自分の亡き後も「乙女」達に命が尽きるまでこの地に立ち続けてほしいと願ったこの詩。激しく綴る言葉とは裏腹に「乙女」達への温かみが感じられる不思議な詩である。
高村光太郎は、上野公園の『西郷隆盛像』を製作した高村光雲の長男として生まれた。偉大な父への反発と明治という文明開化の潮流。そして、妻、長沼智惠子との出会いは高村光太郎に独特の女性への視点を持たせることになる。仏師から身を起こし、勇ましさ、猛々しさを見るものに感じさせる光雲の作品に対して、裸婦像を中心とした光太郎の作品は、繊細で女性への感性が現代的だ。
実際に見る「乙女の像」は、広く張っている肩、大地を踏みしめるような力強い足のラインが目を引く。大自然に負けないような人間としての強さ。それは、生命の再生を果たす「乙女」の姿であり、社会が作り出した「か弱い存在の乙女」とは一線を画する。智惠子の晩年を見続けた高村光太郎の女性への視線は、男としての度量の広さを感じる。『智恵子抄』へまで昇華させた高村光太郎の女性観はフェミニストのそれに他ならないと言えるのだろう。